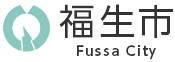令和6年度児童手当の制度改正
児童手当の申請はお済みですか。
主な変更点(令和6年10月以降)
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代に延長
- 第3子以降の支給額を月額30,000円に増額
- 多子加算のカウント対象を大学生年代(22歳に到達する年度末まで)に延長
- 支払月を年6回(偶数月)に増加
制度改正の内容
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。改正後の初回支給は、令和6年12月になります。
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
|---|---|---|
| 支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 を養育している市内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 を養育している市内在住の方 |
| 所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
| 手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
| 支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
| 多子加算のカウント対象※ |
高校生年代まで (18歳に到達した年度末まで) |
大学生年代まで (22歳に到達した年度末まで) |
※多子加算のカウント対象について
多子加算とは、大学生年代のお子さんを含め、上から3人目以降のお子さんの児童手当が加算される制度です。大学生年代のお子さんをカウントに含めるには、親等(受給者)がそのお子さんの生活費や学費等の大半を負担し養育している場合に限ります。これに該当する方は、「【新規】認定請求書または【額改定】認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。(結婚や就職により親等から独立して生計を営むようになった場合は、カウントには含められません。)
手続きについて
制度の改正に伴い、児童手当の受給に申請が必要となる場合がありますので、次のフローチャートを御確認の上、次のとおり手続きを行ってください。
現在、受給されている公務員の方は、こちらの手続きは不要ですので、勤務先の手続きを確認してください。
原則、電子申請でお願いいたします。
※電子申請には、事前に御用意して頂く書類があります、こちらは請求者(受給者)本人のみの手続きとなります。
※中学生以下のお子さんのみを養育しており、現在児童手当を受給しているご家庭は申請不要です。
提出書類
●児童手当認定請求書 または ●児童手当額改定認定請求書
フローチャートを参照のうえ、該当の請求書の届出をしてください。
●請求者の健康保険証の写し
フローチャートにて【新規】認定請求書の場合は、提出が必要です。
●請求者の口座内容の分かるものの写し
フローチャートにて【新規】認定請求書の場合は、提出が必要です。
●別居監護・生計同一申立書
請求者が新規の支給対象児童(0歳から高校生年代まで)と別居かつ監護している場合は、提出が必要です。この申立書は、別居の支給対象児童のみについて記入する書類になります。
こちらの提出方法については、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童(0歳から高校生年代まで)と大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまで)の子を含めて3人以上養育している場合は、提出が必要です。この確認書は、大学生相当の子について記入する書類になります。支給対象児童のみで3人以上の場合は、不要です。
こちらの提出方法については、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。
●請求者の本人確認書類の写し
郵送で提出する場合は、一緒に御提出ください。
顔写真付きの場合は1種類、顔写真なしの場合は2種類提出が必要です。
【例 顔写真付きの本人確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳・在留カード 等
【例 顔写真なしの本人確認書類】
健康保険証・(特別)児童扶養手当証書・母子健康手帳・年金手帳・源泉徴収票 等
※提出後、必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。御了承ください。
提出方法
窓口での受付は混雑が予想されます。
原則、電子申請または郵送での提出をお願いいたします。
お手数をおかけしますが、御協力をお願いいたします。
注意事項
(1)児童手当の請求者(受給者)については、次のいずれかに該当する方になります。
●児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)となります。
所得が高い方が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
●父母指定者
父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。
●未成年後見人
●児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
(2)令和5年分の所得が未申告の場合は、市・都民税の申告を行ってから請求の手続きをしてください。
申請期限
令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、制度改正後の令和6年10月分から支給します(受給資格がある方に限ります)。なお、令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※添付書類につきましても、上記期限までに提出してください。
電子申請はこちら
電子申請には、上記の<提出書類>のほかに、次のものを御用意し、請求者(受給者)本人が該当の請求手続きを行ってください。
▼【新規】認定請求
●マイナンバーカード
●署名用電子証明書暗証番号(半角の6文字から16文字英数字が混在したもの)
●スマートフォン
●「マイナサイン」アプリのダウンロード
▼【額改定】認定請求
●スマートフォン
●請求者(受給者)本人確認書類できる書類
※顔写真付きの場合は1種類、顔写真なしの場合は2種類提出が必要です。
【例 顔写真付きの本人確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳・在留カード 等
【例 顔写真なしの本人確認書類】
健康保険証・(特別)児童扶養手当証書・母子健康手帳・年金手帳・源泉徴収票 等
提出書類のダウンロード
請求書
-
【新規】認定請求書 (PDF 222.9KB)

-
【新規】認定請求書 記入例 (PDF 479.2KB)

-
【額改定】認定請求書 (PDF 299.7KB)

-
【額改定】認定請求書 記入例 (PDF 383.9KB)

その他必要書類
次の書類の提出については、電子申請ができません。お手数ですが郵送か窓口での提出をお願いいたします。
-
別居監護・生計同一申立書 (PDF 55.2KB)

-
別居監護・生計同一申立書 記入例 (PDF 121.7KB)

-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 132.8KB)

-
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF 414.5KB)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737